オートサンプラーはHPLCやUHPLCに欠かせない装置です。この記事では、オートサンプラーの構造と注入方式の違いを整理し、圧力域や流路材質など、選定のポイントを解説します。また、洗浄手順とよくあるトラブルへの対処法も紹介します。この記事を読めば分析条件に適したモデルを絞り込み、運用時の悩みも事前に解消できるでしょう。
分析計測ジャーナルでは、オートサンプラーに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
HPLCオートサンプラーの概要と基本構造
HPLCのオートサンプラーは試料を自動でインジェクタに導入し、手動注入に伴うばらつきや作業負荷を大きく減らします。130MPaを超える超高圧領域でも安定した注入ができるので、再現性・定量精度は手動に比べてとても高いです。オートサンプラーは夜間・休日を含む24時間連続運転が可能なので、分析効率が飛躍的に向上します。
オートサンプラーが試料を注入する基本メカニズムを解説し、シリンジ計量機構について整理します。仕組みを押さえれば、装置選定やトラブルシューティングが格段に取り組みやすくなりますよ。
HPLCオートサンプラーの心臓部!6方バルブの基本構造
出典:島津製作所 LC-MS用オートサンプラ選定時に考慮すべきこと
オートサンプラーの心臓部は 6 方バルブです。レオダイン社やバルコ社のものが有名ですが、最近は各メーカーが独自のバルブを開発しています。
6方バルブの計量法として最も普及しているのが、シリンジ計量方式です。シリンジ計量法では以下のような流れで注入が進みます。
1.LOAD位置でシリンジがサンプルをループに充填
2.バルブがINJECT位置に切り替わると、移動相がサンプルを押し流しカラムへ送液
UHPLCでは微小漏れが致命的となるため、ニードルシールには、PEEKやルビーといった高耐圧・耐摩耗性に優れた材料が一般的に使用されます。
注入方式の種類と特徴
オートサンプラーの注入方式は「全量注入(ダイレクト)」「全量注入(固定ループ)」および「部分注入」の3つに大別されます。
| 項目 | 全量注入(ダイレクト) | 全量注入(固定ループ) | 部分注入(ループ一部充填) |
| 注入方法 | サンプリングニードルで計量した試料の全量を注入 | 固定ループで計量した試料の全量を注入 | サンプリングニードルで計量した試料の一部を注入 |
| 再現性 | 高い | 高い | シリンジ精度に依存 |
| サンプル使用量 | 少量 | 多め | 少し多め |
| 適用分野 | 定量分析 微量サンプル分析 | 定量分析 | 汎用的に使用 |
| 特徴 | 試料ロスがない | メンテナンスが簡単 自動前処理機能に最適 部分注入(ループ一部重点)としても使用可 | メンテナンスが簡単 自動前処理機能に最適 |
| 注意点 | 大量注入では注入時間がながくなる。コストが高め | 全量注入として注入量を変えるには、サンプルループの交換が必要 | マイクロリットル以下では分析値のばらつきに注意0.5μL以下ではデッドボリュームを考慮する |
オートサンプラーの選定ポイント

最適な一台を選び抜くには、分析目的・注入量・キャリーオーバー対策など複数の視点を総合的に比較する必要があります。以下では、とくに判断材料となる三つの軸を整理しました。実際の選定で重要となる具体的なポイントを、失敗例も交えながら解説していきます。
分析目的に合わせた機種選定
機種選定を成功させるためには、分析が通常のHPLCなのか、UHPLCなのか、またはセミミクロ分析なのかを明確にすることが重要です。筆者も以前、UHPLC対応と思って購入した機種が耐圧不足で使用できなかった経験があります。
機種選定で注目すべきは、流路の内径と素材です。セミミクロカラムを使用する場合、サンプラー内の拡散を極小化するため、流路径が0.1mm以下のものが理想的です。また、分析対象によってはステンレス製よりもPEEK製の流路の方が吸着が少なく、回収率が格段に向上します。
見落としがちなのが処理能力の観点です。多検体処理が必要な場合は、それに応じた堅牢性も重要な選定要素です。
注入量と精度のバランス
注入量の検討は選定において重要な要素です。微量分析向けであれば0.1μLレベルから注入可能なタイプ、セミ分取用であれば最大10mLクラスの注入量が必要になります。
注入精度も重要な選定基準です。定量分析では注入精度が結果を左右するため、CV値(変動係数)を十分に確認しましょう。1μL注入時にCV 1%以下を保証しているモデルは、精度の高い機種です。
ニードル先端の形状も重要な要素で、傾斜カットタイプは気泡巻き込みを抑える効果があります。カタログ値と実測値が異なる場合もあるため、可能であれば実機でテストすることもおすすめです。
キャリーオーバー対策と洗浄システム
キャリーオーバー対策と洗浄システムは、オートサンプラー選定において重要な検討要素です。特に低濃度と高濃度を交互に測定する場合において、前のサンプルが微量でも残存すると、分析結果の信頼性に深刻な影響を与えます。
実測値で0.005%以下のキャリーオーバーを保証している機種は高精度なオートサンプラーです。洗浄システムは各社が工夫を凝らしており、単純に洗浄液に浸すタイプから、積極的に洗浄液を送り込むアクティブタイプ、さらには超音波洗浄機能を備えたハイエンドモデルまで様々な方式があります。
化合物の物理化学的特性(LogP値や解離定数など)によって吸着性は大きく変わるため、分析対象の性質を十分に考慮する必要があります。分析対象が吸着しやすい化合物である場合には、洗浄機能を特に重視して検討しましょう。
島津製作所のオートサンプラーの特徴

出典:島津製作所 マルチプレートオートサンプラ SIL-30ACMP
オートサンプラーの選定を検討する際、国内外の多くのメーカーから様々な製品が販売されており、どれを選ぶべきか迷うことも多いでしょう。島津製作所のオートサンプラーは、国産メーカーならではの細やかな配慮と、長年の分析機器開発で培った技術力が魅力です。
SILシリーズを中心とした製品ラインナップは、通常のHPLCからUHPLCまで幅広いシステムに対応し、特に日本の分析現場のニーズを熟知した設計となっています。ここでは、島津製作所のオートサンプラーが持つ具体的な特徴と、それらがどのような分析場面で威力を発揮するのかを詳しく見ていきます。
SILシリーズの特徴
島津製作所のオートサンプラーには、SIL-40シリーズやSIL-30ACMPがあります。
SIL-40シリーズの特徴
- 超高速サイクル:注入サイクルは最短 7秒以下
- 超低キャリーオーバー:内部リンスを併用すると 0.0005 %以下に抑制
- 高耐圧・広い注入量レンジ:最大 130 MPa に対応し、0.01–100 µL(オプションで 2 mL)まで設定可能
SIL-30ACMPの特徴
- マイクロプレート対応:本体に最大 6 枚の96/384ウェルプレートを収容
- 低キャリーオーバー:マルチリンス機能により、0.0015%以下
自動前処理機能と応用例
近年のモデルは、注入だけでなく自動希釈や誘導体化反応もサンプラー内部で完結できます。アミノ酸分析におけるOPA誘導体化のように反応時間の管理が結果を左右する場面でも、プログラム制御によりばらつきが減少。夜間に自動希釈と連続測定を行う運用も現実的になり、作業負荷と分析時間の短縮が期待できます。島津製作所では、自動前処理装置も開発しておりオートサンプラーと組み合わせると、より正確で素早い測定ができます。
| 自動前処理ができる製品名 (機種名をクリックするとカタログにリンクします) | 自動前処理機能 |
|---|---|
| MUP‑3100 | 抗体糖鎖の全自動前処理 |
| ATLAS‑LEXT NHD | 液/固相抽出(スタンダード) |
| ATLAS‑LEXT GHD/VHD | 液/固相抽出+遠心・乾固(ハイエンド) |
| CLAM‑2040/2030 | LC‑MS用 前処理全自動化 |
他メーカーのオートサンプラーの特徴一覧
HPLCのオートサンプラーは、島津製作所以外にも多くの優秀なメーカーが存在します。それぞれが独自の技術と特徴を持ち、異なるニーズに対応した製品を展開しています。以下に主要メーカーの特徴をまとめました。
| メーカー | 代表機種 (機種名をクリックするとカタログにリンクします) | 特徴 | 適用分野 |
| アジレント | 1260シリーズ | 高精度注入、優れた耐久性、豊富なアクセサリ | 医薬品分析、品質管理 |
| ウォーターズ | ACQUITY UPLC Sample Manager | 超低分散、UPLC専用 | 高速分析、バイオマーカー、代謝物解析 |
| サーモフィッシャー | Vanquish Split Sampler HT / FT | 高速処理、優れた洗浄性、低キャリーオーバー | 環境分析、食品分析、バイオ医薬品 |
| JASCO | AS-4050 オートサンプラー | 国産メーカー、コストパフォーマンス重視 | 研究開発、教育機関 |
| 日立ハイテク | Chromaster 5280 Autosampler | 操作の簡便性、メンテナンス性 | ルーチン分析、食品分析 |
アジレントテクノロジーのオートサンプラーは、再現性と信頼性に定評があり、医薬品分析や規制対応が必要な分野で広く採用されています。ウォーターズはUHPLC技術の先駆者として、超高速分析に特化した設計です。
サーモフィッシャーサイエンティフィックのVanquishシリーズは、バイオ分析向けの機能が充実しており、タンパク質や抗体医薬品の分析に適しています。国産メーカーではJASCOや日立ハイテクが、使いやすさとコストパフォーマンスを重視した製品を提供しています。
各メーカー独自の強みを持っているため、分析目的と予算に応じて最適なメーカーを選びましょう。
オートサンプラーの洗浄機能と重要性
オートサンプラーは試料注入の自動化だけでなく、注入後に流路へ残る成分をいかに素早く、確実に除去できるかがデータ品質を左右します。洗浄機能はキャリーオーバー低減の要で、高感度分析や濃度差の大きいサンプルの連続では欠かせない評価項目です。キャリーオーバーが発生する仕組みを整理し、洗浄方式・洗浄液選定のポイントを紹介します。
キャリーオーバーのメカニズム
キャリーオーバーは、ニードル表面に残る薄膜、ループ内の微量残留成分、配管接続部に入り込んだ試料など、複数の経路で発生します。塩基性化合物はシラノール基との相互作用が強く流路へ吸着しやすいです。薬物動態研究のような高感度分析では 10⁻⁴ %台の残留でも検出される恐れがあります。痕跡量分析に携わる研究者は、洗浄パラメータの最適化が欠かせません。
効果的な洗浄方式の比較
洗浄方式には大きく分けて3種類あります。
- 洗わない(無洗浄)
- 浸すだけ(パッシブ洗浄)
- 積極的に洗浄液を流す(アクティブ洗浄)
実験データを見ると一目瞭然で、Chlorhexidineなどの吸着性の高い化合物では、アクティブ洗浄が圧倒的に効果的です。数値で見ると、無洗浄では約0.07%のキャリーオーバーが発生するのに対し、パッシブ洗浄では約半分、アクティブ洗浄では約1/3まで低減できます。
(出典:島津製作所LC-MS用オートサンプラ選定時に考慮すべきこと)
さらに最近は超音波洗浄機能を備えたオートサンプラーも登場し、洗浄液の種類を選ばず強力な洗浄が可能です。装置価格は上がりますが、再測定やデータ欠損に伴う損失を抑えられるため、長期的にはコストメリットが見込めます。
サンプル特性に合わせた洗浄液の選択
洗浄液はサンプルの性質に応じた選択が必要です。
- イオン性化合物:対イオンを添加すると静電吸着が抑えられ、残留が大幅に減少。
- 疎水性化合物:アセトニトリルやメタノールを50%以上含む洗浄液が有効。
- タンパク質/ペプチド:界面活性剤を微量添加すると脱着が促進。
さらに、ニードルや流路材質も洗浄液選定に影響します。PTFEやPEEKコーティングは疎水性が高く、特定化合物の吸着を低減できるケースが多いです。筆者は酸性・中性・塩基性の三種類を常備し、サンプル特性に合わせて使い分けていますが、この体制でほとんどの分析条件がカバーできます。
HPLCオートサンプラーの保守と管理
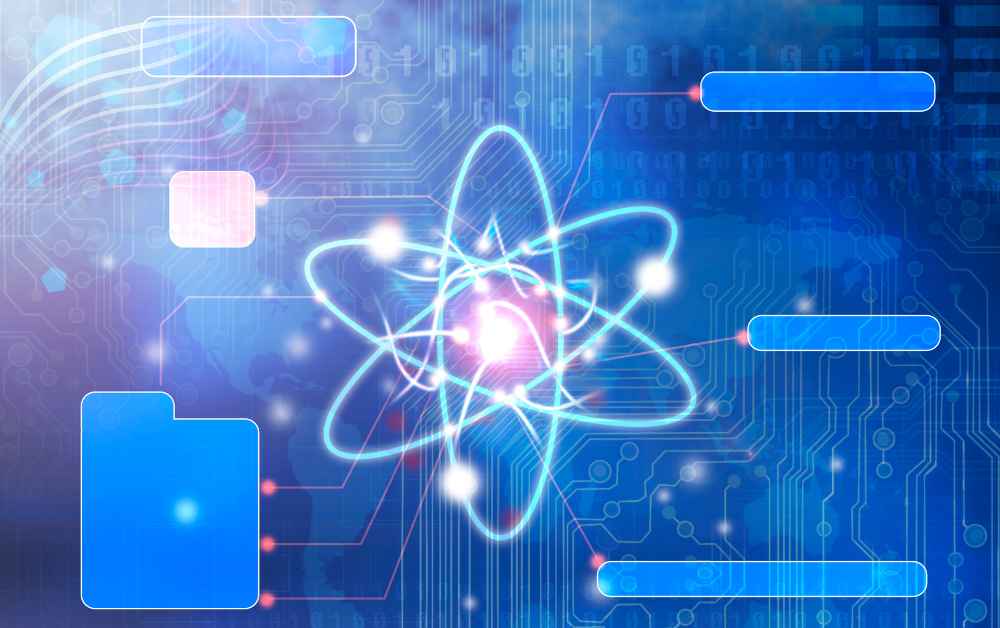
HPLCのオートサンプラーは、日常的に次の項目をメンテナンスしていると、長く安定して使えます。
・注射針やサンプルループの定期的な洗浄:
洗浄を怠ると微粒子の堆積やタンパク付着が進み、流量ズレを招きやすいです。
・シリンジの交換:
シリンジは消耗品。おおむね1000〜2000回の注入で交換時期が訪れる
・プランジャーの点検:
表面の微細な擦り傷も注入精度に影響するため、目視で点検
・微生物や塩の析出の抑制:
週末の分析終了後に、有機溶媒で全体をフラッシュ。特に緩衝液使用後は50%メタノールでの洗浄が効果的
・塩溶液や強酸・強塩基溶液後の洗浄:
中性の溶媒でしっかり洗い流す。特にリン酸緩衝液は乾燥すると結晶化して詰まりの原因になるため、使用後の洗浄は念入りに
・バルブのローターとステーターの点検:
月1回程度、接触面を点検
・長期停止時の保管方法:
80%イソプロパノールで流路を満たし、栓を閉じて保管する
オートサンプラーのよくあるトラブルと解決方法
オートサンプラーを使っているとよく起こるトラブルと対処方法を一覧に挙げました。トラブルに遭遇したら、この表を参考にしてください。
| 症状 | 主な原因 | 対処法 |
| キャリーオーバー | ニードル表面・ループ内残留 | 高極性溶媒での追加洗浄、ニードル洗浄速度の再設定 |
| 注入精度低下 | シリンジ摩耗、気泡混入、過大バックプレッシャー | シリンジ交換、ライン脱気、配管閉塞の有無を確認 |
| 流路詰まり | 結晶析出、微粒子堆積 | 逆方向洗浄(0.1 M 希塩酸 → 中性洗剤 → イソプロパノール)によるフラッシュ |
| バルブリーク | ローターシール摩耗 | ローター/ステーターセットの交換 |
オートサンプラー導入のメリットと投資対効果

オートサンプラーは再現性の向上や作業効率アップだけでなく、長期的なコスト削減にも直結する装置です。手動注入との精度差や労働時間の削減効果を数値で示し、投資回収モデルを示します。導入を迷っている方が費用対効果を判断しやすいよう、具体例を交えてメリットを整理しました。
手動注入との精度・再現性比較
かつては手動注入で十分と考えていましたが、オートサンプラーを導入してから再現性の差に驚かされました。同一サンプルの繰り返し注入で変動係数(CV値)を比較すると、手動では 2〜5 %程度のばらつきが出る一方、オートサンプラーでは0.5%以下に収まるケースが多く見られます。0.1µLの極微量の注入でも、最新モデルならCV約1% を達成でき、結果の信頼性向上に直結します。
労力削減と作業効率の向上
手動注入では検体ごとに装置の前を離れられませんが、オートサンプラーなら一括セット後は自動運転が可能です。100検体規模の分析例では、作業時間が4〜5時間短縮され、夜間運転も実現しました。そのため1日の分析数が3倍近くに増加しました。
分析中はデータ処理や別作業に集中できるので、研究者一人あたりの生産性が大幅に高まります。
長期的なコスト削減効果
オートサンプラーの導入には初期費用が必要ですが、人件費圧縮、再試験削減、装置稼働率向上が積み重なり、総コストは手動注入より約 30〜50%低くなる試算が得られました。人の技量に左右されない再現性は規制対応にも有利で、導入から2年で投資額を回収した例もあります。品質管理や多検体処理を担う現場ほど効果が大きいので、導入を検討してみましょう。
まとめ
オートサンプラーは高い再現性と夜間連続運転が可能で、HPLCやUPLCには欠かせない存在です。機種選定のときには、圧力域、流路径・材質、注入量、洗浄性能を重点的にチェックしましょう。日常洗浄と消耗部品の予防交換が安定稼働を支えます。オートサンプラーを導入して、効率的な分析を進めましょう。
分析計測ジャーナルでは、オートサンプラーに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
記事をシェアする
