
分析計測ジャーナルは、研究現場と社会実装をつなぐ視点で最前線の取り組みを伝えています。今回は、同志社大学・北岸宏亮教授にインタビュー。人工血液の探索から転じて一酸化炭素(CO)を捕まえるhemoCDの着想に至った経緯、非臨床・GLP対応や大学発ベンチャー構想までのロードマップをうかがいました。あわせて、オイルフリー化など日々の運用改善、装置のシェアを前提にした「壁のないラボ」という理想の研究空間、青山商事との長年の協働、そして次世代研究者へのメッセージも紹介します。
人工血液探索からCOを捕まえる着想へ

同志社大学北岸研究室では、有機合成を基盤に、生体分子の機能を模倣する化合物の設計をしています。ヘモグロビンの働きを再現するhemoCD(ヘモCD)も、その流れの中で生まれました。
環状オリゴ糖であるシクロデキストリンの機能を活用して生まれたhemoCDの出発点は、人工血液の実現可能性を探る試みでした。しかし実験を重ねても体内滞留性が十分でなく、血中に長く留まらないという課題に直面していました。ところが、尿中に排出されたhemoCDが一酸化炭素(CO)を強固に捕捉していることを偶然発見し、CO中毒の解毒剤としての方向性に舵を切りました。
CO中毒は事故や火災、日常の不慮の出来事として現在も頻繁に発生していますが、有効な解毒薬は存在しません。もしhemoCDを用いた医療現場での治療法が確立できれば、現場の医師にとっては待望の選択肢となり、患者さんの生存率や予後を大きく改善できる可能性があります。
医療現場における保存のしやすさや使い勝手も踏まえて、凍結乾燥粉末製剤として保管し、使用時に注射用水で溶解して静脈投与する方法を考えています。将来的には筋肉注射や経口の可能性も探索したいと考えていますが、まずは点滴投与で最大の有効性を確認する段階です。
スケールアップやGLPの壁とベンチャー構想|医療実装へのロードマップ

現在は医薬品としての製品化にむけた準備段階です。具体的には、GLP(Good Laboratory Practice)準拠の安全性評価、薬物動態、製剤安定性のデータ整備を順次進めています。合成方法そのものは研究室で確立していますが、医薬品としての品質一貫性を担保するには、合成ルートの最適化とスケールアップ、規格設定が不可欠です。
スケールアップには大型装置と製造環境が必要です。またGLP評価用に適した品質の製剤も、これから作らなければなりません。各種規制を厳守しつつ進めるのは、これまでの基礎研究とは違った壁がいくつもあります。
CO中毒解毒剤の開発については、製薬企業に何度も話をしにいきましたが、ほとんどの場合は既存の得意領域から外れるテーマであることがわかりました。このことを踏まえ大学発ベンチャーを自ら立ち上げ、一定の段階まで開発を自力で進める構想を持っています。知財の整理、開発資金の確保、経営・開発人材の組織化など、研究の外側の要件にも正面から取り組むつもりです。救急の医師からは「現場で使いたい」という声をすでに多くいただいており、社会的意義の大きさを強く感じています。この製剤によって1人でも多くの命を救えるのではないか。そう考えると、研究を進める責任と意義の重さを改めて感じます。
非臨床から臨床へとつなげるまでには長い道のりがありますが、社会的なインパクトは計り知れません。ベンチャーとして実用化まで粘り強く進め、いずれは救急医療の標準治療の一つとして根付かせたいと考えています。
オイルフリー化と安全・効率の両立

日々の研究を支えるのは、地道な運用改善だと考えています。数年前より反応時の加熱はオイルバスからアルミブロックへ切り替え、温度制御をデジタルで安定化しました。真空ポンプは油回転式ではなく、高性能のダイヤフラムポンプに変えました。これにより研究室で油を使うことがほとんどなくなり、油汚れの除去や有機溶剤を用いた洗浄の頻度が減り、実験台・ドラフト内の清潔さが保ちやすくなりました。
私が学生のころは使用済み溶媒を蒸留し、洗浄用への使い回しや、金属ナトリウムを使って脱水溶媒を作る、という作業も毎日のようにしていましたが、これらは手間がかかる上に危険も伴う作業でした。近年は高品質な溶媒が低価格で手に入るということもあり、購入試薬に切り替えました。すると安全性と効率性が両立し、研究スピードも同時に高められました。
理想の研究空間とは?「壁のないラボ」が生む交流

私には理想のラボをデザインしたいという夢があります。それは複数の研究グループが一つの大空間で緩やかに共存する「壁のないラボ」です。装置エリアと執務エリアを緩やかに分けつつ、視線と動線が交差する配置にする。偶然の会話や観察から新しい発想が生まれる状態を常態化したいと考えています。
分析装置は専有ではなくシェアを前提にし、誰も使っていない時間帯にすぐ使える運用ルールとし、装置の重複投資を減らし、稼働率を上げられます。教授室は奥まった個室ではなく、学生の前を自然に通る位置に置いてコミュニケーションの頻度を高める設計にしたいです。
この発想の原点には、アメリカで経験したラボの環境があります。広い空間をゆるやかに区切りながら、異なる教授の研究グループがエリアごとに分かれており、研究者同士が行き来しながら自然に議論を交わしていました。ラボを出れば、ソファやコーヒースペースが設けられ、研究の合間にリラックスした雰囲気で交流できる。その何気ない会話からも新しい研究アイデアに結びつく場面を何度も目にしました。
私も、そんな「実験と雑談が地続きになる空間」を本学でも形にしたいと願っています。風通しのいいラボは装置のシェアを進め、研究効率を上げるだけでなく、学生や研究員のモチベーションや発想力を育てる土壌にもなると信じています。
青山商事と築いた長期的な信頼関係

青山商事には、実は私が学生のときから約20年にわたって、お世話になっています。装置導入や講習会の手配、さらに依頼分析の取りつぎまで、長く支えてもらっています。また、現場の使い方に合わせた講習やメンテナンスの段取りを、いつも迅速に整えてもらっています。
担当の方が変わっても関係が途切れず、必要なときにすぐ相談できる点は大きな安心材料です。学生の入れ替わりにより使える人がいなくなってしまった装置についても、講習を組んで再立ち上げをしてもらったことも何度もあります。顔の見えるやり取りの積み重ねが、研究室運営の安定に直結していると感じます。
次世代研究者に伝えたいこと
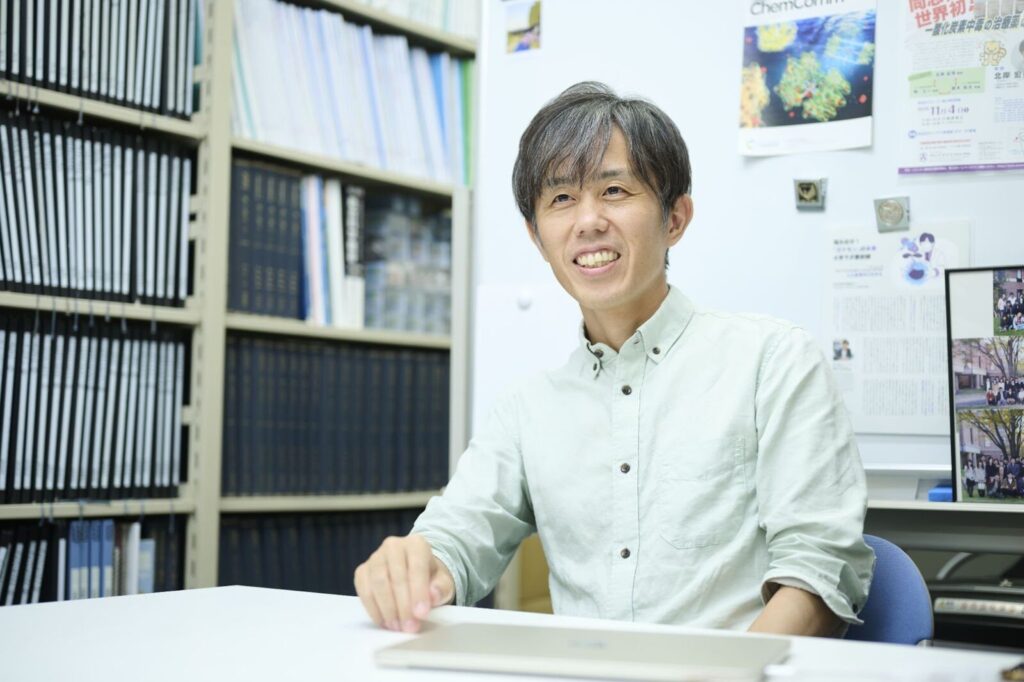
研究の原点は、科学そのものへのロマンだと考えています。たとえば、溶液中で分子が働く様子を想像して楽しむ心、それをスペクトルを通して表現できること、または単純にエバポレーターで溶媒が蒸発する様子を眺めて楽しいと思える感覚、色、におい、などなど。その面白さに正直でいてほしいです。実用性は後からついてきます。
私の研究室では、学生たちは多彩なテーマに挑戦しています。たとえば、ミトコンドリアの機能を模倣する分子モデルの設計や、シクロデキストリンを応用して脳へ薬剤を届けるドラッグデリバリーの研究などがあります。医薬応用に直結するテーマもあれば、どこに使えるかまだ分からない純粋に合成化学として面白い構造を追いかける研究もあります。これらのテーマを通して、多くの実験経験を積んでほしいと思っています。
安全を守りつつ、自分で考え、試し、経験する自由を手放さないことが、大学の研究室では最も大切で、新しい発見に直結します。博士課程への進学は、その自由度と視野を大きく広げる選択肢でもあります。研究は本来、時間の裁量が大きい働き方です。自分のペースで深く考え、粘り強く手を動かす力が、次のブレークスルーを連れてくると信じています。
お話をお伺いしたのは...

【同志社大学 理工学部 機能分子・生命化学科】
教授 北岸 宏亮氏
- 同志社大学で学位取得後、大阪大学工学研究科・博士研究員、同志社大学助教/准教授、米・Scripps Research研究員を経て現職
- 研究分野:有機合成、超分子化学、生物無機化学
- 研究テーマ:ヘモグロビン機能模倣化合物「hemoCD」を用いたCO中毒治療薬の開発、シクロデキストリンを用いたドラッグデリバリー研究、ミトコンドリアなどの生態機能モデルの設計・合成など
分析計測ジャーナルでは、新技術や最新の分析機器のご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ライター名:バッハ
プロフィール:大手製薬会社において約8年間新薬の開発研究携わる。新薬の品質を評価するための試験法開発と規格設定を担当。さまざまな分析機器を使用し、試験法検討を行うだけでなく、工場での品質管理部門にも在籍し、製薬の品質管理も担当。幅広い分析機器の使用経験があり、数々の分析トラブルを経験。研究者が研究に専念でき、遭遇するお悩みを解決していけるよう様々な記事を執筆中。
記事をシェアする
