
ICP-OES(誘導結合プラズマ発光分光分析法)は、元素を高感度で測定できる分析手法で環境分析・食品検査・医薬品品質管理・半導体材料分析など、多様な分野で活用されています。ICP-OESを販売しているメーカーは数多くありますが、どのメーカーの製品がよいのか?あるいはどんな特徴があるのか?という点がイマイチ分かりにくいこともありますよね。
そこで本記事では、ICP-OESの主要メーカー5社(島津製作所、Thermo Fisher Scientific、日立ハイテク、Agilent Technologies、PerkinElmer)の最新機種を比較し、選び方のポイントを詳しく解説します。
分析計測ジャーナルでは、ICP-OES選定に関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
ICP-OESの基本原理と測定方式の違い

ICP-OES(誘導結合プラズマ発光分光分析装置)については、別記事に原理などを詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。
今回はその記事での補足説明として、ICP-OESのタイプの違いから話をはじめます。
ICP-OESには、マルチタイプ(同時型)とシーケンシャルタイプ(逐次型)の2種類があります。装置選びの際は、どちらのタイプが適しているかを理解することが重要です。ここでは、タイプの違いについて簡単に解説します。
マルチタイプ(同時型)とは?
マルチタイプは、複数の元素を同時に測定できる方式です。分光器にCCD検出器やフォトマルチプライヤを搭載し、発光スペクトルを一括で取得するため、測定時間が短縮されます。その特徴は以下の通りです。
- 1回の測定で複数の元素を解析できる
- 測定時間が短いので、大量のサンプルを分析するラボに適している
- 一般的に高価格だが、長期運用ではコストパフォーマンスが良い
シーケンシャルタイプ(逐次型)とは?
シーケンシャルタイプは、1元素ずつ順番に測定する方式です。分光器内のグレーティングを回転させながら各元素のスペクトルを取得していきます。測定時間は長くなりますが、装置の価格が比較的安価なことに加え、特定元素を高精度に測定できます。
- 1元素ずつ順番に測定するため、測定時間が長め
- 装置価格が比較的安価で、コストを抑えたいラボに適している
- 高い分解能を持つ装置が多く、特定の元素を精密に測定可能
ICP-OESを選ぶ際は、分析する元素の種類や試料数、運用コストを考慮し、適切な測定方式を選択することが重要です。
主要メーカー5社の技術比較
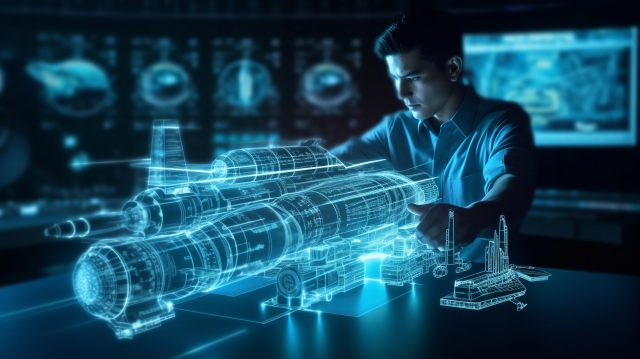
ここからは、各メーカーの特徴と製品について比較していきます。
島津製作所(Shimadzu)ー環境負荷を抑えた省エネモデル
島津製作所のICP-OESは、低コスト・高精度・省エネルギー性能を兼ね備えた装置として、環境分析や医薬品分析など幅広い用途で採用されています。
他にも、以下の点が強みです。
- 冷却水不要設計により、ランニングコスト削減
- アルゴンガス消費量を約50%削減
- プラズマの安定性に優れ、長時間測定でも分析精度を維持
- 国内メーカーならではの充実したサポート体制
マルチタイプのICPE-9800シリーズは濃度に関わらず多元素を一斉かつ高速で分析できるだけでなく、使いやすいソフトウェアを導入している点が特徴です。参考価格は1,875万円〜で業界最高水準のローコスト化も実現しており、さまざまな分野で利用されています。
シーケンシャルタイプのICPS-8100はシーケンシャル分光器を2台搭載しており、高分解能と高速分析を両立しました。操作性にも優れ、品質管理から研究開発まで幅広く活躍してくれるでしょう。参考価格は3,140万円〜です。
Thermo Fisher Scientificー初心者向けの直感的な操作性
Thermo FisherのICP-OESは、初心者でも使いやすい直感的な操作性と高い分析精度を両立しています。高分解能光学系を採用しており、スペクトル干渉を最小限に抑えるだけでなく、AIによるスペクトル補正機能を搭載して、測定誤差を低減しています。環境モニタリングや医薬品分析にも適した設計です。
iCAP PROシリーズは、高スループットな光学系と電荷注入素子検出器を組み合わせた高速分析を実現しています。iFR分析モードなら1回の測定でスペクトル全体が取り込まれ、分析時間はさらに短縮。微量成分を精度よく分析したい方におすすめです。また、iCAP PROシリーズでは操作画面のガイド機能や自動最適化機能が充実しているため、測定条件の設定に不慣れな研究者でもスムーズに分析を進められます。
Agilent TechnologiesーAIを導入した無駄のない分析
Agilent Technologiesは、デュアルビュー技術を活用した高感度測定が可能で、特に環境試料や食品、石油化学試料の分析に適しています。
いずれもマルチ型の5800シリーズと5900シリーズを展開しており、分析結果を解析して最適な波長を教えてくれる機能や、メンテナンスのタイミングを知らせる機能が搭載されているのが特徴です。信頼性の高い分析結果が得られるだけでなく、再測定やダウンタイムによるムダを減らせます。
Agilent TechnologiesのICP-OESは、AIを導入することで装置の異常を予測し、問題を事前に察知。そのため、機器の突発的な故障を防ぎ安定した稼働ができるので、稼働率を最大限に高められます。たとえば測定途中に機器トラブルが発生した場合、そのサンプルは再測定になりますが、事前にトラブル回避ができていれば再測定すべきサンプル数は極限までカットできるのです。AI導入により最短時間で正確な結果を得られます。
日立ハイテク(Hitachi High-Tech)ー高感度かつ低コスト運用を実現
日立ハイテクは、島津製作所と同じく国内メーカーならではのきめ細かなサポート体制があります。また小型・省スペース設計な装置を展開しているため、小規模ラボでも使いやすいのが特徴です。
マルチ型のSPECTRO ARCOS FHX3Xを使えば、高感度かつ干渉を最小限に抑えた精度の高い分析ができます。アキシャル・ラジアル(シングルまたはデュアル)プラズマ測光を1台の装置内に搭載した、マルチビューICP-OESです。
シーケンシャル型のPS3500DDIIシリーズは、従来機に比べて分析速度が大幅に向上したほか、アルゴンガスの消費量も従来の半分となっており、低コストかつ高分解能が特徴。波長分解能は世界最高水準です。
PerkinElmerーコストの大幅削減と卓越した検出下限値を実現
PerkinElmerのICP-OESは、小型設計ながら高精度な測定が可能で、設置スペースが限られている環境に適しています。
Avio220Maxは、コンパクトながら優れた分解能とサンプルの前処理の最小化を実現しました。
Avio550/560Maxは、非常に複雑な分析対象にも対応できる「真の同時測定システム」を導入した、研究者にとって強い味方です。
ICP-OESの用途別の選び方

ICP-OESは、環境分析、食品検査、医薬品品質管理、金属・半導体材料分析など、幅広い分野で使用されています。各分野に必要な性能と、おすすめ機種を一覧にまとめました。
| 測定分野 | 環境分析(水質・土壌・大気など) | 食品・医薬品分析 | 金属・半導体材料 |
| 測定対象 | 水質中の貴金属土壌中の微量元素大気中の微粒子成分 | 食品中のミネラル成分医薬品中の不純物 | 合金中の微量成分半導体材料の超微量不純物 |
| 必要な性能 | ・高感度分析 ・マルチ型がおすすめ ・長時間でも安定したパフォーマンス | ・低濃度元素が測定可能な高感度分析 ・高い再現性 ・高いメンテナンス性(信頼性確保のため) | ・pptレベルの超高感度分析 ・高分解能でスペクトル干渉を抑える機能 ・高温環境下での安定性 |
| おすすめ機種 (機種名をクリックするとHPにリンクします) | ICPE-9800シリーズ iCAP PROシリーズ 5800シリーズ | iCAP PROシリーズAvio550/560Max ICPE-9800シリーズ | PS3500DDIIシリーズ 5900シリーズ |
ICP-OESのランニングコストの詳細と削減方法

ICP-OESの導入には本体価格だけでなく、ランニングコスト(消耗品・ガス・メンテナンス費用)が発生します。長期的に安定して運用するためには、ランニングコストの管理が重要です。
ランニングコストの内訳
ICP-OESの運用には、以下のようなコストが発生します。
| 費用項目 | 内容 | 年間コスト目安 |
| アルゴンガス | プラズマ発生用 | 50~200万円 |
| 冷却水・電力消費 | 水冷式だとチラーが必要 | 30~100万円 |
| 消耗品交換 | トーチ・ネプライザー・スプレーチャンバーなど | 10~50万円 |
| メンテナンス費用 | メーカー点検や修理など | 20~100万円 |
これらを合計して、年間110〜450万円が必要です。
ランニングコストを削減する方法
ランニングコストを削減するためには、以下の方法がおすすめです。
・アルゴン消費量の少ない装置を選ぶ:避けては通れないアルゴンガス消費。最近ではガス消費量を抑えた装置が展開されているので、導入の際に検討するとよいでしょう。
・冷却水不要の装置を選ぶ:島津製作所のICPE-9800シリーズは、冷却水が不要なのでコストをカットできます。
・メンテナンスが簡単な装置を選ぶ:複雑な装置設計なので、メンテナンススケジュールの把握のためにiCAP PROシリーズなど、自動診断機能付き装置を選ぶのも手です。
最新技術動向(AI・自動化・省エネ)
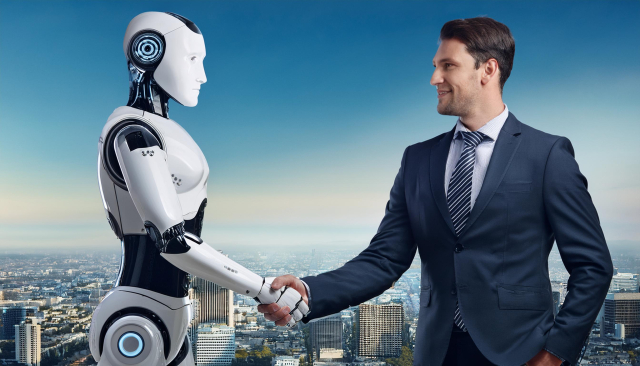
近年ICP-OESの技術革新が進み、AIによる測定補正、装置の自動化、省エネルギー設計が強化されています。
AIによるスペクトル解析
AIを効果的に使うことで、ヒューマンエラーを減らした効率的な分析ができます。たとえばThermo FisherのiCAP PROシリーズは、AIがスペクトル干渉をリアルタイム補正します。Agilent Technologiesの5900シリーズは自動補正機能により測定のばらつきを抑制。これらの機能は忙しい研究者をサポートしてくれるでしょう。
自動化技術の進展
自動化機能を搭載したAgilent Technologiesの5800シリーズは自己診断機能でトラブルを未然に防止します。Thermo FisherのiCAP PROシリーズは自動洗浄機能でメンテナンスの手間を軽減してくれます。
省エネルギー設計
コストを抑えるだけでなく、環境負荷を減らすという意味でも省エネルギーは重要なキーワードです。島津製作所のICPE-9800シリーズは、冷却水が不要なだけでなく、アルゴンガス消費量を抑えてくれるので、ランニングコストを大幅に削減してくれます。PerkinElmerのAvio550/560Maxは小型&省エネ設計で消費電力の削減に大きく貢献します。
まとめ

本記事では、ICP-OESの主要メーカー5社を比較し、詳しく解説してきました。
- 低ランニングコストの運用かつきめ細かなサポート体制:島津製作所のICPE-9800
- 初心者でも扱いやすい操作性:Thermo FisherのiCAP PROシリーズ
- AIによる無駄のない分析:Agilent Technologiesの5800/5900シリーズ
- 低コストかつ高分解能:日立ハイテクのPS3500DDIIシリーズ
ICP-OESの導入を検討している方は、用途に適した装置を選ぶことが重要です。運用コストも考慮しながら適切な機種を選びましょう!
分析計測ジャーナルでは、ICP-OES選定に関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
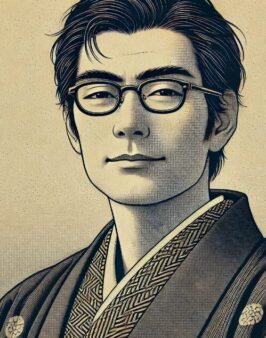
ライター名:西村浩
プロフィール:食品メーカーで品質管理を10年以上担当し、HPLC・原子吸光光度計など、さまざまな分析機器を活用した試験業務に従事。現場で培った知識を活かし、分析機器の使い方やトラブル対応、試験手順の最適化など執筆中。品質管理や試験業務に携わる方の課題解決をサポートできるよう努めていきます。
記事をシェアする

