
GC-MSやLC-MSは分析化学の現場で欠かせない技術ですが「違いがよく分からない」「どちらを使えばいいのか迷う」と悩んでいませんか?
GC-MSとLC-MSは食品・医薬品・環境・法医学など幅広い分野で活用されていますが、対象物や目的によって選ぶべき手法は異なります。そこで本記事では、GC-MSとLC-MSの基本原理から最新技術、具体的な活用事例、導入・運用のポイントまで詳しく解説します。さらに、AI解析や環境負荷低減といった最新トレンドにも触れていきます。
この記事を読むと、GC-MSとLC-MSの違いと適切な使い分けが理解できるでしょう。分析の精度向上や業務の効率化に役立ててください。
分析計測ジャーナルでは、GC-MS・LC-MSに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
GC-MSとLC-MSの基本原理
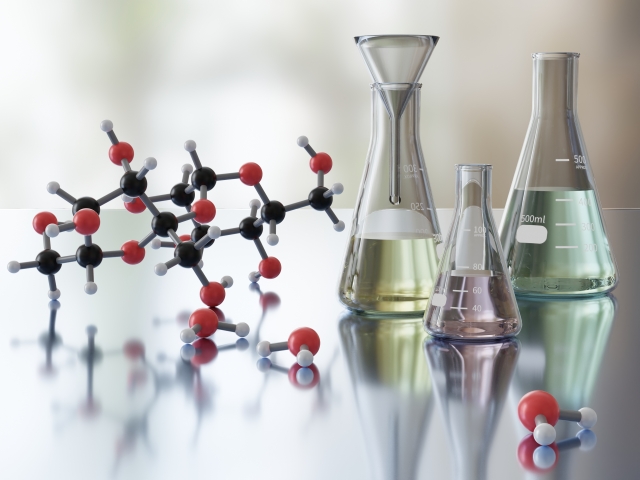
GC-MSとLC-MSは、それぞれクロマトグラフィー技術(GCまたはLC)と、質量分析技術(MS)を組み合わせた分析法ですが、構造や原理には大きな違いがあります。ここでは、それぞれの技術を詳細に解説します。
GC-MSの基本原理
GC(Gas Chromatography:ガスクロマトグラフィー)は、気化した化合物をキャリアガスとともに移動相として流し、固定相と相互作用させることで分離する手法です。GCの主要な構成要素は以下のとおりです。
キャリアガス
試料を移動させるためのガス(一般的にはヘリウムや水素)が使用されます。
インジェクター
試料を気化し、カラム内に導入します。
カラム
化合物を分離するための管状の固定相(一般的にはシリカキャピラリーカラム)が使用されます。
検出器
カラムを通過した化合物を検出し、信号を生成します。
分離の原理は、化合物の蒸気圧と固定相との親和性の違いに基づきます。一般的に揮発性の高い化合物ほど早く溶出し、固定相との相互作用が強い化合物ほど遅く溶出します。
GCにおける質量分析(MS)の原理
ガスクロマトグラフィー(GC)によって分離された各成分は、質量分析部(MS)へ送られ、そこでイオン化→質量分析→検出というプロセスを経て測定されます。
GC-MSの最大の特徴は「電子イオン化(EI)」による詳細なフラグメント情報の取得と「ライブラリ検索による化合物同定力の高さ」です。そのため、揮発性有機化合物の高精度な定性・定量が可能です。
イオン化(Ionization)
GCから送られてくる試料はカラム内で気化され、気体の状態で質量分析計に導入されます。最初のステップでは、この気体分子をイオン化して荷電粒子に変換する必要があります。
GC-MSで最も一般的に使用されるイオン化法は以下の通りです。
| イオン化の種類 | イオン化の手順 | 特徴 | 適用例 |
| 電子イオン化(EI) | 分子に電子ビームを照射し、電子を弾き出してイオン化 | 強いエネルギーで特有のフラグメントを生じるので、ライブラリ検索しやすい | 有機溶媒、香気成分、VOC、農薬など |
| 化学イオン化(CI) | メタン・アンモニアなどと反応させてイオン化 | フラグメントを抑えた分子イオンピークが得やすい | 分子量確認、複雑な混合物の測定補助 |
この工程では、分子がフラグメント(断片化)することで、化合物特有のスペクトルパターンが得られます。特にEI法は、そのフラグメント情報がNISTなどのライブラリデータベースと照合可能であることが大きな強みです。
質量分析(Mass Analysis)
イオン化された分子やフラグメントは、質量対電荷比(m/z)に基づいて質量分析計(アナライザー)内で分離されます。GC-MSでは、用途や求められる精度によって以下のアナライザーが使い分けられます。
| 質量分析計の種類 | 特徴 | 適用例 |
| 四重極型(QMS) | m/zを選択的に通過させる 高速・高精度な定量 | 環境分析、食品分析 |
| トリプル四重極型(TQ-MS) | MS/MS測定できる 高感度・高選択的に検出 | 農薬、ダイオキシン、微量毒物分析 |
| 飛行時間型(TOF-MS) | 高速・高分解能 未知成分の同定や正確な質量測定 | 複雑試料、スクリーニング分析 |
| 磁場型(Sector-MS) | 非常に高い分解能・質量精度 | 超微量毒物、環境汚染物質の精密分析 |
このプロセスによって、対象化合物の質量情報が得られ、同定・定量・構造解析できるようになります。
検出・スペクトル解析
分離されたイオンは、イオン検出器(電子増倍管など)で捕捉され、電気信号に変換されます。この信号はマススペクトルとして出力されます。
【スペクトル解析のポイント】
- 横軸:m/z(質量対電荷比)
- 縦軸:イオン強度(量)
- 各ピークの位置→化合物の特性・フラグメント情報
- ピークの高さ→化合物の存在量(定量情報)
特にGC-EI-MSでは、得られたスペクトルがNISTなどの標準ライブラリと一致するかを照合し、未知化合物の同定精度を高めることが可能です。
また、トリプル四重極型GC-MS(GC-MS/MS)を用いれば、ターゲット成分を選択的に検出するMRM測定が可能となり、食品中の微量農薬や環境中の微量有害物質の厳密な定量にも対応できます。
LC-MSの基本原理
LC(Liquid Chromatography: 液体クロマトグラフィー)は、液体を移動相として使用し、カラムの固定相との相互作用を利用して化合物を分離する手法です。GCと異なり、揮発性が低く、熱に不安定な化合物も分析できます。主な構成要素は以下のとおりです。
移動相
一般的には、水や有機溶媒(メタノール、アセトニトリル)が使用されます。
ポンプ
移動相を一定の圧力でカラムに送ります。
インジェクター
試料を移動相に導入します。
カラム
化合物を分離するための固定相(一般的には逆相カラムや正相カラム)が詰められたチューブです。
検出器
カラムから溶出した化合物を検出し、データを記録します。
LCの分離の原理は、移動相と固定相との親和性の違いに基づきます。例えば、逆相クロマトグラフィー(Reverse Phase Chromatography, RP-HPLC)では、疎水性の強い化合物ほど固定相に保持され、後から溶出します。
LCにおける質量分析(MS)の原理
液体クロマトグラフィー(LC)によって分離された各成分は、質量分析部(MS)へと送られ、そこでイオン化→質量分析→検出というプロセスを経て測定されます。LC-MSの最大の特徴は、「ソフトイオン化」と「高感度な質量分析」によって、熱に弱い化合物や高分子化合物まで高精度に分析できる点です。
イオン化(Ionization)
LCから送られてくる試料は液体のまま質量分析計に入るため、最初のステップでイオン(荷電粒子)に変換する必要があります。これをイオン化と呼びます。
LC-MSで主に使用されるイオン化法は次の2つです。
| イオン化法の種類 | イオン化の手順 | 特徴 | 適用例 |
| エレクトロスプレーイオン化(ESI) | 高電圧をかけて微細な液滴にし、溶媒を蒸発させながらイオン化 | 多価イオン化することで、高分子も測定可能 | ペプチド、タンパク質、医薬品など |
| 大気圧化学イオン化(APCI) | 高温で気化させ、コロナ放電でイオン化 | 疎水性・低極性の化合物に強い | 農薬、脂溶性ビタミンなど |
この工程で、対象化合物を壊すことなく「イオン化」することで、高感度な測定が可能になります。特にESIは、ペプチドやタンパク質など熱や衝撃に弱い化合物の測定に強みを発揮します。
質量分析(Mass Analysis)
イオン化された化合物は、「質量/電荷比(m/z)」に従って質量分析計内で分離されます。LC-MSでは、分析目的や対象化合物に応じて、以下のようなさまざまな質量分析装置(アナライザー)が使い分けられます。
| 質量分析計の種類 | 特徴と役割 |
| 四重極型(QMS) | m/zを選択して通過させる。特定化合物の定量に強み。 |
| トリプル四重極(TQ-MS) | ターゲット化合物をMS/MS(MRM)で選択的・高感度に測定。医薬品・農薬の微量分析に最適。 |
| 飛行時間型(TOF-MS) | 高速・高分解能。正確な質量情報から未知化合物を同定 |
| Orbitrap | 超高分解能・高質量精度。複雑なサンプルでも高精度な測定。 |
この工程によって、対象化合物の質量情報が得られ、構造解析や定量分析につながります。
検出・スペクトル解析
分離されたイオンはイオン検出器で捕捉され、電気信号として記録されます。この信号は「マススペクトル」として出力され、横軸がm/z(質量/電荷比)、縦軸がイオン強度(量)を示します。
- 各ピークの位置→「どの化合物か」を示す
- ピークの高さ→「どれくらいの量存在するか」を示す
特にトリプル四重極型(MRM測定)では、対象物質だけを高感度・高選択的に検出できるため、食品中の農薬や生体試料中の微量薬物など、厳密な定量が求められる場面で活躍します。
GC-MSとLC-MSを選ぶ基準と応用分野
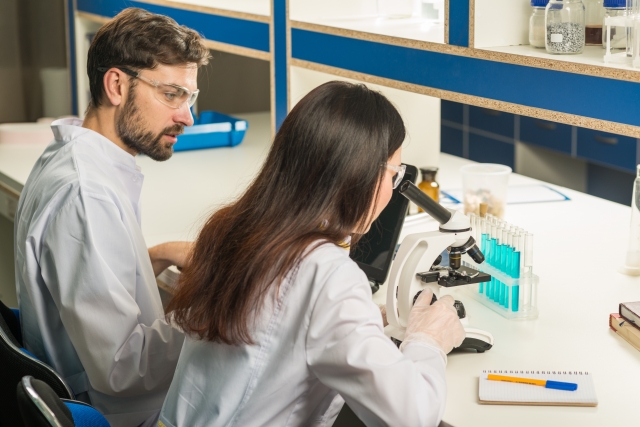
GC-MSとLC-MSは、それぞれの特性に応じて適した分析対象が異なります。どの場面でどちらを選択するべきかを理解することで、適切な分析手法を選べます。
GC-MSとLC-MSを選ぶ基準とは?
GC-MSとLC-MSの選択は、分析対象の物理化学的特性によって決定されます。
| 特性 | GC-MSが有利 | LS-MSが有利 |
| 揮発性 | 高い | 低い・非揮発性 |
| 熱安定性 | 強い | 弱い |
| 分子量 | 小さい(~1,000Da) | 大きい(~数万Da) |
| 極性 | 低い | 高くても測定可能 |
| イオン化特性 | EIによるフラグメント解析 | ソフトイオン化で高感度分析 |
| マトリックスの影響 | 少ない | 大きい |
さらに分析の目的によって、検出感度も選定します。高分解能での成分特定なら高分解能MS(HR-MS)、定量分析が必要であればトリプル四重極型MS(TQ-MS)がよいでしょう。
試料の状態によっても、GC-MSかLC-MSのどちらが適しているか異なります。例えば液体の生体試料(血液、尿)を分析する場合はLC-MSが適切で、気体の環境試料(空気、大気中のVOC)を分析する場合ならGC-MSの方がよいです。
GC-MSとLC-MSの応用分野
GC-MSとLC-MSはそれぞれ異なる特性を持つため、以下のような応用分野で利用されています。
| 分析法 | 応用分野 | ||
| GC-MS | 環境分析 空気中の有機化合物測定 水質・土壌中の有害物質の測定 | 食品分析 香気成分の分析 食品中の異臭物質の特定 残留溶媒の測定 | 法医学・薬物分析 血液や尿中の薬物・毒物の検出 犯罪捜査の証拠物質分析 |
| LC-MS | 医薬品開発 新薬の有効成分の定量・同定 代謝物の解析バイオマーカーの測定 | 食品安全管理 食品中の農薬や抗生物質の残留分析 食品添加物のモニタリング | 生体試料分析 タンパク質、ペプチド、脂質の定量 血液や尿中のバイオマーカーの解析 メタボロミクス研究 |
例えば環境中の有機溶媒、食品中の香気成分、薬物検査などにはGC-MSが適しています。一方、バイオ医薬品の品質管理、食品の農薬残留分析、代謝物の分析にはLC-MSが多用されています。
このように、分析対象の特性や目的に応じて、適切な分析手法を選ぶことがポイントです。
最新技術の進歩と応用事例

近年、GC-MSやLC-MSの技術は大幅に進化しており、より高感度・高分解能な測定ができるようになりました。ここでは最新の技術動向と、それらがどのように活用されているかを紹介します。
GC-MSの最新技術
GC-MSは日々進歩しています。その最新技術をいくつかご紹介しましょう。
高分解能GC-MS(HR-GC-MS)
高分解能マススペクトルを取得し、微量成分の同定精度が向上しました。また、環境汚染物質や複雑な混合物の解析に有効です。
二次元ガスクロマトグラフィー(GC×GC-MS)
2つの異なるカラムを組み合わせることで、複雑な試料の分離能が高くなっています。食品や香料の分析、石油製品の解析に活用されています。
迅速分析技術(Fast GC-MS)
カラムの短縮や加熱制御技術を最適化することで、分析時間が短縮されました。大量の試料を素早く処理する必要がある環境や製薬業界で有用です。
LC-MSの最新技術
LC-MSも負けていません。日々進化を続けており、複雑な分析にも対応できるようになっています。
超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC-MS)
粒径の小さいカラム充填剤を使用したことで、高分離能を実現。分析時間を短縮しつつ、より詳細なデータを取得できるようになりました。
高感度MS/MS(トリプル四重極、Orbitrap)
トリプル四重極(Triple Quadrupole)を導入し、特定の化合物を高精度で定量します。Orbitrapは、超高分解能で未知化合物の同定に役立ちます。
イオンモビリティ分光法(IMS)との統合
質量分析の前に、分子の形状や構造情報を分析します。立体異性体の分離や、複雑な生体試料の分析に応用されています。
最新技術の使用事例
それぞれの分野ごとに「どの技術や測定法がどのように役立っているのか」を具体的に解説します。
バイオ医薬品(抗体医薬)の品質管理
抗体医薬は分子量が大きく、構造も複雑なため、揮発性のないLC-MSが必須です。
また、ペプチドマッピング(酵素消化後のペプチド断片をLC-MSで解析)によって、アミノ酸配列の確認、修飾部位の特定、糖鎖構造解析ができます。さらにMS/MSによる高感度・高選択性分析で不純物検出も可能です、
創薬過程でのターゲット分子のスクリーニング
LC-MS(ハイスループットスクリーニング)の中でもトリプル四重極MSの技術が使われています。
化合物ライブラリーから候補化合物を迅速にスクリーニングし、活性分子を同定します。LCで分離後、MSで化合物ごとに質量測定することで特定・定量可能です。MS/MS(MRM)で特定ターゲットを高感度検出し、薬効評価につなげています。
食品分野
食品分野では、高分解能GC×GC-MSによる食品のフレーバープロファイリングが行われています。2次元ガスクロマトグラフィー(GC×GC)+高分解能MS(HR-MS)の組み合わせです。
複数の異なる極性カラムを用いたGC×GCで、複雑な香気成分を詳細に分離します。HR-MSによる高精度な質量測定で、類似した化合物の同定精度が向上しました。食品の風味・香り成分の微量分析に活用(コーヒーやワインの品質評価)されています。
LC-MSを用いた事例だと、食品中の抗生物質の検出が挙げられます。抗生物質は極性が高く熱不安定なものが多いためGC-MSでは困難です。そこでLCで分離後、MS/MS(MRMモード)で標的化合物を高感度・高選択的に定量します。規制値以下の微量レベルまで検出可能で、食品安全検査に必須の技術です。
法医学・環境分野
2つの事例を紹介します。まずは、HR-GC-MSによる微量毒物の検出です。
高分解能ガスクロマトグラフ質量分析(HR-GC-MS)によって、EIイオン化によるフラグメント情報から化合物を同定します。高分解能測定により、マトリックスからの背景干渉を除去し、極微量毒物(pgレベル)でも特定可能です。法医学では遺体や血液、尿などから毒物検出、環境分野では土壌や水中の微量有害物質分析に活用されています。
もう一つがGC×GC-MSを利用した大気汚染物質の同定です。2次元ガスクロマトグラフィー(GC×GC)+MSを組み合わせています。大気中のVOC(揮発性有機化合物)やPAHs(多環芳香族炭化水素)など複雑な成分群を詳細に分離します。高感度なMS検出により、環境基準以下の微量レベルの物質まで定量可能です。大気汚染の原因物質特定や、都市・工場排出ガスの解析などに活用されています。
現場で使える!GC-MS・LC-MSのプチ情報

GC-MSやLC-MSの導入は、単に機器を購入するだけでなく、適切な運用やデータ解析のノウハウが必要です。本章では、分析精度を向上させるための工夫・トラブルシューティングについて詳しく解説します。
分析精度を向上させるための工夫
分析の再現性や正確性を高めるためには、いくつかの前処理技術やメソッドの最適化が重要です。
前処理技術
固相抽出(SPE):試料中の夾雑物を除去し、目的成分を濃縮します。GC-MS・LC-MS両方に共通です。
誘導体化(GC-MS用):揮発性の低い成分を化学修飾し、分析しやすくします。
メソッド開発の最適化
移動相の選択(LC-MS):分析対象に応じた最適な溶媒を選定します。
カラム温度・流速の調整(GC-MS):分離能に大きく影響します。
トラブルシューティング
分析装置を運用していると、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。代表的な問題とその対処法を以下に示します。
| 問題 | 原因 | 対策 |
| ピークが出ない | 試料が適切に導入されていない | インジェクター・スプリッターの詰まりをチェック |
| ピークが広がる | カラムが劣化している | カラムを交換する |
| 感度が低い | イオン源が汚染された | イオン源をスクリーニング |
今後の展望と技術トレンド

分析技術の進化は目覚ましく、今後もさらなる高感度化・高分解能化が進むと考えられます。ここでは、今後の技術トレンドを紹介します。
AIとデータ解析の融合
近年、人工知能(AI)を活用したデータ解析が注目されています。特に、機械学習技術を組み合わせることで、従来の質量分析データの解析精度が大きく向上しました。
具体的な応用例
- AIによるスペクトル解析の自動化により、ピーク同定や定量解析を効率化します。
- データのばらつきや異常値をAIが自動検出してくれるので、品質管理に役立ちます。
マルチオミクス解析との統合
LC-MSを用いたプロテオミクス(タンパク質解析)やメタボロミクス(代謝物解析)が進化しており、ゲノム解析(DNA解析)と組み合わせたマルチオミクス解析ができるようになりました。
この技術は、創薬・疾患研究・栄養学など、さまざまな分野で活用されています。
環境負荷低減のための新技術
従来のクロマトグラフィー技術では、多量の溶媒が必要でしたが、最近では環境に配慮した分析技術が注目されています。
- 水系移動相を用いたグリーンHPLCでは、有機溶媒の使用を抑えて環境に配慮した分析ができます。
- 低溶媒消費型LC-MSシステム:溶媒消費量を削減し、ランニングコストを低減します。
まとめ

本記事では、GC-MSとLC-MSの基本原理から最新技術、応用事例、導入・活用のポイントまでを詳しく解説しました。
- GC-MSは揮発性の高い化合物、LC-MSは非揮発性・高極性化合物の分析に適している
- GC-MSは環境分析や食品香気成分の測定、LC-MSは医薬品・バイオマーカー分析に活用
- 最新技術として、高分解能MS、AI解析、エコフレンドリーな手法が登場
- 機器導入時には、分析対象や目的に応じた最適な装置選定が重要
- 精度向上のための前処理技術やトラブルシューティングを活用
今後、AI解析の発展やマルチオミクス解析との統合が進み、より高度なデータ解析が可能になると予想されます。また、環境負荷低減を意識した持続可能な分析技術が求められるでしょう。今後の技術動向を把握し、最新の分析技術を取り入れることが、研究者や分析技術者にとって重要です。
分析計測ジャーナルでは、GC-MS・LC-MSに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ライター名:西村浩
プロフィール:食品メーカーで品質管理を10年以上担当し、HPLC・原子吸光光度計など、さまざまな分析機器を活用した試験業務に従事。現場で培った知識を活かし、分析機器の使い方やトラブル対応、試験手順の最適化など執筆中。品質管理や試験業務に携わる方の課題解決をサポートできるよう努めていきます。
記事をシェアする
